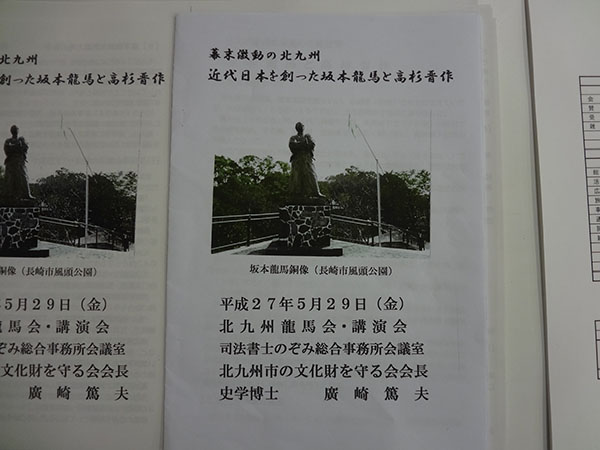活動ログ
第5回定例会の記録
2015.11.30 更新
5月29日に第5回定例会が開催されました。
今回は、北九州市の文化財を守る会会長で史学博士の廣崎篤夫先生にご講演頂きました。廣崎先生は、文化センター等にて歴史講座の講師をされており、戦国時代から近代までの歴史に深く精通されておられます。
また、「福岡県の城」(海鳥社)などの著書があり、郷士の歴史についても各地で講演されています。
今回のテーマは「幕末激動の北九州 近代日本を創った坂本龍馬と高杉晋作」と題して、龍馬と晋作についてをその生い立ちからその功績までを解説して頂きました。
まず身分制度の視点から、坂本家と高杉家の当時の階級について石高を中心に見ていきました。当時の身分には、上士、下士の他に、足軽や中間といった階級があり、江戸時代がいかに階級社会だったかがよく分かりました。
特に、坂本家は土佐藩の郷士だったという話は有名ですが、高杉家というのは毛利藩の大組士という200石の上級階級でした。晋作は超エリートの家柄だったのです。廣崎先生曰く「NHK大河ドラマ花燃ゆでは、高杉晋作は立派な着物を着ているでしょ!」などと身近な例を取って、とても分かり易く解説をして頂きました。
廣崎先生のお話では、龍馬はこの土佐藩の厳しい身分制度に嫌気がさして脱藩したとのことでした。実際に、龍馬は脱藩する時に下駄を持っており、他藩で履いていたというエピソードがあるそうです。龍馬と言えばブーツのイメージが強いですが、また違った側面を見ることが出来ました。
身分制度という観点から言えば、晋作が入門した松下村塾は身分を問わず誰でも入塾できたとのことです。高杉家は200石という話がありましたが、久坂玄瑞は25石、伊藤博文や山県狂介は中間といったように、当時塾には身分にとらわれず幅広い人材が出入りしていました。
この「来る者拒まず」の吉田松陰の思想が、高杉晋作が創設する奇兵隊に引き継がれていきます。晋作は上海滞在中に、太平天国の乱を目撃し、欧米列強による中国の半植民地化の実態を目の当たりにしました。
そこで帰国後、下関で奇兵隊の結成に取り掛かります。正規でない軍隊ですが、やる気、元気、本気があれば入れたとのことです。当時としては、あまりに斬新な人材登用です。
一方、脱藩により身分制度から解放された龍馬は、勝海舟や西郷隆盛など多くの知己を得ていきます。そして、薩摩藩の後盾を得て、長崎を拠点に社中を結成します。操船技術を買われてのことでした。
封建社会の中で、新しい組織を築いていった龍馬と晋作は、幕府による長州再征伐いわゆる小倉戦争(豊長戦争)で協力することになります。龍馬は、長州藩海軍総督に就任した晋作より、小倉口の幕府軍との戦いへの援軍を求められたのでした。
このように今回は、近代日本を創った龍馬と晋作という観点から、講義して頂きました。
奇しくも龍馬と晋作は、新しい世を見る前に倒れてしまいました。しかし、廣崎先生の解説を聴いていて、操船技術に基づく龍馬の社中(後の海援隊)、あるいは、身分を越えた晋作の奇兵隊がいかに日本の近代化の礎だったかがよく分かりました。
また、龍馬の社中によって、長州奇兵隊の武器が近代化したことを考えると、二人が日本の近代化に与えた影響は図りしれません。
身分を越え、混迷の時代に立ち向かった二人の行動力を、今こそ我々は学ぶべき時ではないでしょうか。